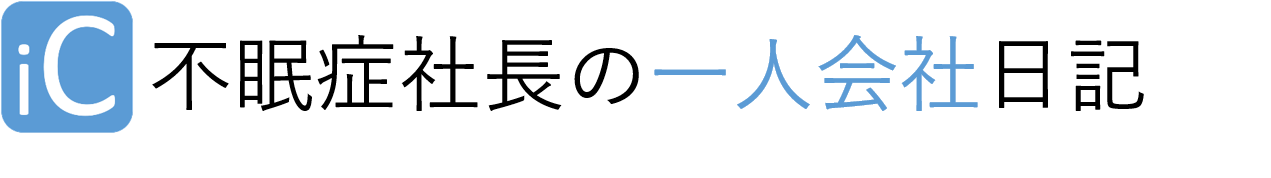サピエンス全史
ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳、河出書房新社、2016
ホモサピエンスは神話のような虚構を信ずる性質があったために発展した。宗教もイデオロギー思想も民主主義も平等主義も資本主義も貨幣経済も、ましてやインターネットやAIや何もかも実態のない虚構(神話)を我々は信じて生きている。仏教でいうところの戯論すなはち空である。いったいこの先はどうなることやら。。。
日本人として知っておきたい琉球・沖縄史
原口泉著、PHP新書 1311、2022
琉球・沖縄の古代から近現代までを概説。日本と中国の二重支配のなかで、日本の琉球支配が中国(明、清)に対して名目上は隠されていたというのは興味深い。地政学的にも大変重要な地だけに、悲しい現実が中世から現代にいたるまで起こってしまう。その中でも豊かな自然を背景に、独自の華やかな文化を築いてきた。
沖縄戦記 鉄の暴風
沖縄タイムス社編、ちくま学芸文庫、2024
沖縄の惨状。沖縄県民の戦死者は現状12万人以上と言われているが、当然一人一人通り一遍で語れるものではない。日本軍が米軍がと一言で表せるものでもない。いずれにしてもこの惨状を二度と繰り返してはならない。
若者よ、マルクスを読もう 20歳代の模索と情熱
内田樹・石川康宏著、角川ソフィア文庫、2010
両先生の往復書簡。「共産党宣言」「ドイツ・イデオロギー」などマルクスの若い頃の著述。史的唯物論:「かれらがなんであるかは、かれらの生産と、すなわちかれらがなにを生産し、またいかに生産するかということと一致する」
原爆の子 広島の少年少女のうったえ (上、下)
長田新編、岩波文庫、1990
広島原爆投下から6年目に綴られた子供たちの手記。父母兄弟姉妹など家族を亡くした者、自ら負傷し生死をさまよった者、疎開先から家族の安否を祈った者。多勢の子供達の生の声。
大系日本の歴史14 二つの大戦
江口圭一著、小学館、1989
第一次大戦から第二次大戦までの通史。日本がいかに破滅の道を歩んできたか。 日本の戦没者310万人に対し、諸外国はその10倍に及ぶ。被害と加害の実相の差を再認識する。 戦争体験の風化が言われるが、被害側にのみ焦点を当てた歪んだ認識であるならば、”風化は惜しくない”という著者のあとがきにハッとさせられる。
レイシズム
ルース・ベネディクト著、阿部大樹訳、講談社学術文庫、2020
原著は80年以上前の古典であるが、現代世界の差別主義、排外主義を見事に表している。というか、当時から何も変わっていない、いやもっと深刻な状態に陥っている。この現代世界を著者はなんというだろう。
フランス革命 歴史における劇薬
遅塚忠躬著、岩波ジュニア新書、1997
フランス革命は劇薬である。そして劇薬とは熱情の噴出である。ブルジョワと大衆の担う革命。劇薬の効能と痛み。ジュニア向けとはいえフランス革命のエッセンスがよくわかる一冊。
百姓一揆
若尾政希著、岩波新書、2018
日本近世は訴訟社会。訴状が寺子屋の教材になるほど、訴訟が頻繁に行われていた。一揆に対するイメージが変わる。歴史史料の読み解き方にも重点が置かれている。
ラフカディオ・ハーン ―虚像と実像―
太田雄三著、岩波新書、1994
ラフカディオ・ハーンを人種主義的な側面など批判的に評価した本。単なる日本の紹介者的な評価ではなく、著書や手紙などの文献から実像を分析している。
アイヌの世界観 「ことば」から読む自然と宇宙
山田孝子著、講談社学術文庫、2019
アイヌの世界観→二元観
宇宙、霊魂、カムイ、動植物、空間認識
空間区分と領有性
動植物が世界観のメタファー
象徴性を帯びた動物→超自然的世界と自然的世界を有機的につなぐ
古事記 現代語訳
太 安万侶 著、稗田 阿礼 著、武田 祐吉 訳、青空文庫、2012
伝統だ、愛国だと騒がしい世なので、新年の徒然に。
詭弁論理学 改版
野崎昭弘著、中公新書、2017(1976初版)
50年前から、いや太古の昔から、詭弁は何ら変わっていない。